The Hydrosphere
and
Socioeconomics
in Modern Asia
科学研究費基盤研究(S):近代アジアにおける水圏と社会経済 ― データベースと空間解析による新しい地域史の探求
Projects
モンスーンと季節的降雨という気候と、海や河川からなる水圏という、水をめぐる2つの条件と人間社会が交差する問題群として、①「自然環境・現象」、②「生産・生活」、③「移動・流通」を設定している。また、エルニーニョによる異常気象が想定されている、1876-78年、1918-20年、1931年を、ベンチイヤーとしてプロジェクトメンバー全体で共有している。そうした上で、問題群①と②に関するテーマとして、「自然災害と社会変動」を、①と③に関するテーマとして「水圏間のつながりと仮想水貿易(Virtual Water Trade)」を設定し、3つのプロジェクトを進めている。
- Home
- Projects
- The Great Famine in India
- The 1931 Yangzi River Flood
- Linkages of Hydrospheres and
Virtual Water Trade
インド大飢饉(1876-78年)研究 -インド中西部デカン地方の旱魃分析
本研究の背景・目的
インド中西部のデカン高原は、モンスーンによる季節的降雨を受けながらも、他方でアフロ・ユーラシア内陸乾燥地帯に属しており、本科研の対象地域の中で、最も乾燥した地域であるといえる。このような環境下では水資源は限られており、歴史的にも、水不足がデカン地方の農業、ひいては人間活動に大きな影響を与えてきた。特に1876年のデカン地方における大規模な旱魃に起因する飢饉は、翌年にインド亜大陸北部で起こった飢饉と連動し、インド亜大陸の大部分に被害をもたらす未曽有の大飢饉となった。1876年から78年まで続いた、この飢饉はインド大飢饉(The Great Famine in India)と呼ばれ、公式的な推計によると約500万人の死亡者が記録され、その数が800万人に上ったとする推計も存在する。インド大飢饉後に、英領インド全土を対象とした飢饉調査委員会が発足され、この調査結果を基に英領インドの飢饉対策が整備された。この点からも歴史的重要性を有するインド大飢饉は、これまで、人口、農業生産、交易、疫病などに関する様々な歴史統計を用いて研究が行われてきたが、飢饉を引き起こした原因が旱魃であるにもかかわらず、気象や水資源に関する統計は十分に活用されてこなかった。本研究の目的は、デカン高原上のインド西部を対象に、モンスーン気候・水圏に注目して、インド大飢饉の発生と、その農村社会への影響を再考することである。
本研究の手法
本研究の新規性は、歴史史資料を用いた歴史学的アプローチと、シミュレーションによる工学的アプローチという二つの異なる手法を組み合わせて、インド大飢饉の発生と影響を再考することにある。
歴史学的アプローチでは、インド西部、すなわち英領インドのボンベイ管区を対象とした飢饉関連史資料の分析を行っている。大英図書館のインド省文書記録(India Office Records)と在インド・マハーラーシュトラ州立文書館ムンバイ本館(Maharashtra State archives, Mumbai)には英領期のボンベイ管区に関する数多くの史資料が収蔵されており、特に後者の収税局飢饉部門(Famine Branch. Revenue Department)には、気象データを含むより詳細な記録が収められている。この飢饉部門の気象データは主に、インド大飢饉が始まる1876年およびその翌年の雨季(6-9月)に関する、日別・月別の雨量記録から成っている。日別の雨量記録は、欠落が多くインド大飢饉時の降雨量の変化を分析することは極めて困難であった。他方で月別の雨量記録は1876-77年の雨季についてデータが連続的に得られ、インド大飢饉以前の降雨量の平均値も記載されているため、当該期間の雨量変化を分析することが可能になる。ただしこれらの雨量データの観測地点は、デカン高原上に位置するボンベイ管区の9県(総面積約114,226㎢)においてわずか24地点であった。気象データを用いた歴史学的なアプローチのみでは、点的な雨量変化を把握するに留まり、水圏という観点からインド大飢饉を再考するのには、データの限界があった。
そこで本研究では、工学的アプローチによってインド大飢饉時の水圏のシミュレーションを作成し、歴史学的アプローチの限界を補うこととした。水圏のシミュレーションを行うにあたり、改めて本研究の対象地域を詳細に設定した。本研究の対象地域であるデカン高原上のインド西部は、インド西海岸に近い西ガーツ山脈を水源としてベンガル湾に注ぐクリシュナ川流域(図1で赤枠内の地域)に属する。本研究ではクリシュナ川流域の中で、その支流であるビマ川流域(図2中の水色で示された領域)に焦点を当てて工学的アプローチを実践した。歴史学的アプローチでは雨量の変化が示されるに留まったが、工学的アプローチでは、農業等の人間活動により直接的に影響を与える変化に注目し、インド大飢饉時の土壌水分量や流水量の変化のシミュレーションを行った。

図1:インド亜大陸とクリシュナ川流域

図2:ビマ川流域と雨量観測点
その後に、本研究では歴史学的アプローチの成果と工学的アプローチの成果の重ね合わせを開始した。両成果は全く異なる方法で導かれており、単純に数値やその変動を比較統合することは極めて困難である。そこでその成果を空間情報として捉え、地理情報システム(GIS: Geographic Information System)を用いて両成果を重ね合わせることで、インド大飢饉の発生状況を再構築することとした。例えば、土壌水分量のシミュレーションのデータは、飢饉部門所蔵の月別雨量データと重ね合わせが可能であり、歴史学的アプローチでは点的にしか把握できなかったインド大飢饉の発生当初の水圏を、工学的アプローチの成果を合わせることで面的に把握することが可能になった(本研究の成果の一端は、ギャラリー参照のこと)。重ね合わせにより明らかとなる、両データの矛盾を解消することが現在の本研究の課題であり、この後にインド大飢饉発生の状況が明らかになる。いくつかの課題が残されており、分析・考察は未完であるが、本研究は、歴史学の研究に新たな方向性を示すものであるといえる。
インド大飢饉が農村社会に与えた影響について、収税局飢饉部門に様々な関連史資料を見出すことができる。例えば、死亡登録報告(Reports on Death Registration)には、1876-77年における地域別の死亡者数、死亡時の年齢、性別、死因などが詳細に記録されている。図3は1876-77年の死因を県別に整理したものであるが、1877年のデカン地方南部の諸県におけるコレラによる死者数(水色部分)が特に伸びていることがわかる(図3参照)。本研究では、インド大飢饉が農村社会に与えた影響を水圏に注目して再考するにあたり、1876-77年のデカン地方における雨量変化と、コレラの流行地域をGISによって重ね合わせ、インド大飢饉時による水圏の変化が、農村社会に与えた影響の一端を示すことを試みた(この成果は、ギャラリーを参照されたい)。
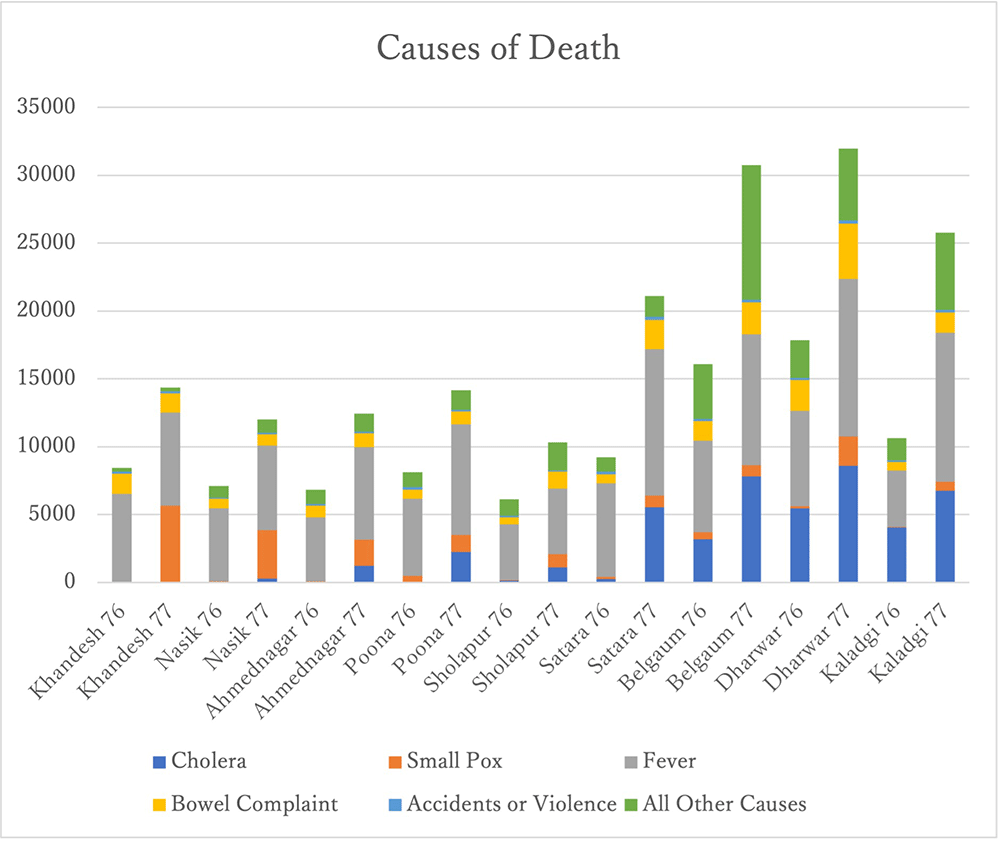
図3:1876-1877年の県別の死亡者数および死因
工学的アプローチの成果を合わせて、インド大飢饉発生当初の水圏とその後の変化を再構築し、その上で、収税局飢饉部門の史資料分析によって得られるインド大飢饉時の諸変化をGISにより比較統合することにより、本研究は、水圏という新たな視点からインド大飢饉を再考することを試みており、現在は、この再考プロセスの途上にある。そしてインド大飢饉が旱魃により発生したことを考えるならば、水圏という新たな視点は、この飢饉を考察する上で欠かすことのできない視点であることは明らかであり、この点に本研究の新規性と重要性がある。(小川 道大)

